
北アルプスの盟主、穂高岳。
穂高と言っても前とか西とか北とか奥とか、いろいろあります。ひっくるめて「穂高岳」。最高地点は奥穂高岳。日本第三位の高さです。
南アルプスの北岳と標高争いではやや遅れをとっています。北アと南アの最高標高がほぼ一致、というのも奇妙な符号ではありますが……。もっとも南アの山々と違い、どの峰もギザギザしています。北アルプス一体は大昔、標高2,800~2,900mの一大高原で、それを氷河期の氷河が削り出していったため同じ高さのギザギザの峰が多数残ったと言います。奥穂はその王様、とでも言うべきでしょうか。(女王様かも知れません)
登山コースは流石に整備されています。とにかく、シーズン中に訪れるハイカーの数は半端じゃないですが、それだけの見応えはあります。素晴らしい山岳風景です。ただ、岩場の歩きは十分な注意を要します。一般登山道でもザイルを出しているパーティがいることからも、その危険度が分かります。歩き慣れて、恐怖感と馴れ合ってしまうよりはマシかも知れません。


穂高岳から富士山を見よう!

穂高岳の周囲はぐるりと高峰が取り巻いているので、それらを超えて富士山方向を眺めることが出来る高度が、まず必要になります。
従って、上高地からの重太郎新道を使った場合は、富士山が見えてくるのは吊尾根の中間点あたりからとなります。早朝から登り始めた場合には、そこまで到達するのに相当時間が掛かっていることと思いますので、雲が湧き出して眺望が隠されてしまう恐れもあります(紀美子平とその手前にも僅かに眺望ポイントがありますが、未確認)。一方、涸沢側から登った場合でも穂高岳山荘ではまだ見えず、山頂付近になってようやく見えるという按配。結局、小屋泊まりにしないと富士山をすっきりと捉えることは出来ないかもしれません。
もちろん、奥穂高岳山頂からは、全方位のパノラマ山岳風景の一角に富士山が眺められます。前穂高岳、涸沢岳、北穂高岳などの峰からでも、富士山は問題なく見えるはずです。ちなみに、蝶ヶ岳~霞沢岳の取り巻きを超えて富士眺望を得られるのは高度2,400m以上。
 | |||||||
吊尾根~前穂~明神岳。遠景、富士山~南ア~中央ア |
手前から奥に上高地、霞沢岳&焼岳、御岳&乗鞍岳 |
ジャンダルム、その左下に西穂 |
笠ヶ岳 |
遠景に黒部五郎・薬師・鷲羽・水晶岳 |
左に立山、右に白馬連山を従えた槍ヶ岳 |
大天井岳~常念岳~蝶ヶ岳、遠景に浅間山 |
|
穂高岳を日帰りで歩こう!
| 日帰りコース | 所要時間 | (登り/下り) | 累積高度 | 登降ピッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 上高地バスターミナル~岳沢~紀美子平~奥穂高岳 (1,504m) |
12時間30分 | 7時間10分 | +1,719m -33m | +240m/h |
| 5時間20分 | -322m/h | ||||
| 2. | 上高地バスターミナル~明神~徳沢~横尾~涸沢~奥穂高岳 (1,504m) |
16時間40分 | 9時間30分 | +1,812m -126m | +191m/h |
| 7時間10分 | -253m/h | ||||

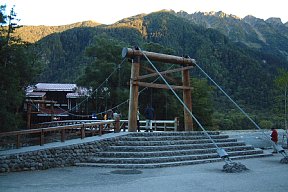

――素直に諦めましょう。
というのは、日帰りで狙うなら上高地からのピストンしかありませんが、上高地には通年マイカー規制が敷かれ、沢渡・平湯の駐車場からシャトルバスで入るしかありません。ゆえに行動可能時間は夏場ハイシーズンあっても最大11時間50分(H25年現在)となります。上高地~山頂往復の最短コースタイムが12時間半ですので、入りません。
それでも日帰りしたいんだ、という向きには……
低山の日帰り直登コースは1時間あたり300~400mを登ることが求められることが多いのですが、この山のコースタイムは240m/時間ほど。山泊装備前提の設定なので、日帰り軽装でスピードを上げられる人ならチャンスも――とは言え、高難度であることは変わりありません。高度差もさることながら、登山道に山泊装備の登山者が多く、結局、回りと合わせた同じペースとなってしまうことが大きいです。結果、下山で急ぎすぎて転倒して怪我とか洒落になりませんので無理はせぬよう。(実例あり)

日帰り山行記 ≫