関ヶ原つわものたちをしのぶみち ≫
東海自然歩道 ≫
関ヶ原
- 古の決戦の地 -
【踏 行 日】2007年2月上旬
【撮影機材】OLYMPUS E-1, ZD14-54F2.8-3.5, ZD50-200F2.8-3.5, CASIO EX-P505
- …(JR東海道線)=関ヶ原駅
- 【アプローチ】滋賀・岐阜県境に程近い関ヶ原。東海道線で向かう。駅前がコース
- 関ヶ原駅~不破の関~エコミュージアム関ヶ原~笹尾山~決戦地~関ヶ原駅
- ★★☆ 史跡を拾いながら巡る半日周回コース。車道が多いが、周囲の小山に立ち寄ることで変化がつく
- 関ヶ原駅~JR醒ヶ井駅=(JR東海道線)…
- 【帰路】もちろん関ヶ原駅から列車に乗るのが普通。今回は、中山道を辿って醒ヶ井まで歩いた。
…(JR東海道線)=関ヶ原駅

関ヶ原というと真白な雪のイメージ――。
たぶん「関ヶ原付近の降雪のため」新幹線が遅れたり止まったりしたという交通情報を、昔、よく耳にしていたせいだと思う。最近、そんな事をあまり聞かなくなったのは、東海道新幹線の対雪能力が上がったためか、それとも気候が変わって雪が少なくなったせいなのか。
でも、関ヶ原には雪の日に行きたいなあ、などとぼんやり考えていたら雪が降った。チャンス!とばかりに翌日の早朝、電車に飛び乗った。目指すは雪原の関ヶ原の地。




米原駅で新幹線から東海道線に乗り換え、東へ向かう。車窓から見えるのは白一面の雪景色。滋賀県と岐阜県の県境の山間部にその地はある。
かくして関ヶ原に到着。
積雪は……5cmほど。期待していた“雪国の豪雪”とまでは行かないけれど、歩けないほどの雪深さだと元も子もない。雪山低山ハイクならたまにするけれど、雪の平地を巡るという経験はあまりしたことが無いわけだし。
関ヶ原駅から外に出る。車道のアスファルト上には、ほとんど雪は無い。2月初旬の厳冬期だけれど、雪のせいで幾分暖かいような気もする。朝の日差しは、確かに弱々しくはあるけれど。
関ヶ原駅~不破の関~エコミュージアム関ヶ原~笹尾山~決戦地~関ヶ原駅


AM8:07、誰もいない関ヶ原駅前からゆるりと歩き始める。
まずは線路に沿って西へ。「関ヶ原古戦橋」で線路を跨ぐと、建物の少ない広々とした風景。そして手前にあるのが東首塚。赤い門が雪に映えている。
中に入る。「首洗いの古井戸」など、少し恐ろしげな史跡。松平忠吉・井伊直政陣跡もここに。


線路を渡り返す。八幡神社に立ち寄ると中山道に出る。ただ、今の中山道は車の往来する国道なので、歩道橋でそれを越えてしまう。
方角を東に転じて、中山道の裏通りを歩き出す。関ヶ原の集落歩きだ。前回歩いた時は夜だったので回りは見えなかったけれど、今、改めて見ると普通の住宅地。雪の積もった畑なども散在している。


緑色の細身の歩道橋で、今度は国道365号を跨ぐ。しばらく見所の無い道。西首塚への分岐も、とりあえずスルーして直進。
左方、関ヶ原中学校が現われた。藤堂高虎陣跡があるとのことだけれど、それらしきものは見当たらない。門の中だろうか? 休日とは言え学校敷地内に立ち入るのには抵抗があるので、パス。


次が、福島正則陣跡だ。今はそこは春日神社になっていて、鎮護するかのように高さ25mの大杉が立ちはだかっている。
――こちらにも紋付の旗が立っている。どうやら、関ヶ原合戦の陣の後には、陣を構えた武将の紋章の旗が立てられているという趣向のようだ。今日のコースは、その陣を1つ1つ巡っていく道でもあるらしい。

AM8:49、不破関跡に到着。ここは東山道の有名な関所。関ヶ原合戦とは直接のゆかりは無い。前回は夜の到着で中に入れなかったけれど、今は門は開いている。
――入る。意外にも庭園になっていた。朝陽が厳かに忍び込んでいる。自分が雪が降ってからの最初の客らしく、雪面に人の足跡は付いていない。踏み荒らすのも勿体無い感じがしたので、見物もそこそこにする。



不破関跡の角に「←東海自然歩道 松尾山 2.4km」の標示。そちらに進む。
民家が消えて林の路地となり、さらに竹林帯を通過。と、鉄道の高架が現われた。ゴトゴトと列車が通過していく、と言うような悠長なものでは無い。ゴアーッという轟音とともに一瞬で列車は過ぎ去っていく――東海道新幹線だ。


次は名神高速道。潜る。
周囲は田園地帯。藤古川の脇を進む。前方に見える松尾山はなだらかなので、ちょっとした森の丘にしか見えない。
――前回は養老から松尾山に登り、明かりの点り始めた関ヶ原を眺めた後、関ヶ原駅まで下りている。だから、この道も逆方向になら歩いたことがある。



ただ、夜道だったので何も見えなかった。今日は松尾山まで戻ってから再出発する算段。松尾山の登山口の駐車場に辿り着く。案の定、周囲の風景に見覚えは無い。
松尾山を登り始める。といっても最初は車道だ。降り積もったままの雪、そこに足跡を付けながら坂を上っていく。
90°右に折れると山道となる。雪の山道――ただ、アイゼンを出すほどじゃない。
←前のコースへ戻る |


AM9:37、松尾山山頂に到着。
山頂広場は雪の原。昨日の降雪からの最初の登山者となるのだろう。足跡1つ無い新雪が美しい。
何はともあれ、関ヶ原方面を見晴らす。関ヶ原の合戦において、ここに陣を置いた小早川秀秋が見たのと同じ、かも知れない光景。
――今日のそれは雪景色。合戦地は、かなり遠く感じる。



西軍でありながら徳川家康と通じていた小早川秀秋。こんな遠くから関ヶ原の戦いの戦況を眺めていて、趨勢が分かるものなのだろうか? いずれにせよ、小早川が謀反を起こして西軍の陣に突っ込んだ結果、天下分け目の決戦の雌雄は決した。
……遠い日の出来事だ。西暦1,600年の往時を偲ぶには少し時代が進みすぎているかも知れない。




AM10:03、松尾山を後に関ヶ原方面へ下山開始――要するに引き返しだ。今日の東海自然歩道歩きは、いちおう松尾山が出発点という設定。
膝下までの雪深い山道を下る。雪深いところは山頂直下だけで、やがてくるぶし程度の積雪の道となる。林の上から関ヶ原が覗けるような箇所もあるけれど、基本は深い林の道。



往、復、往と都合3度歩いている道。当たり前だけれど、雪に付いている足跡は自分が先ほど付けたもの。その足跡を再度踏みしめながら下っていく。勾配は緩やかなので、スピードも出せる。新雪なので、凍っていてスリップという心配も無い。

左折すると、道幅もグッと広くなる。まだ誰一人すれ違う人はいない。ただ、今日の天候なら、これから何人かは雪の低山ハイクに来ることだろうなと思う。


林道は大きくくねって、やがて登山口に出た。登り始めから、ざっと1時間少々経過――だいぶ日も高くなってきた。のどかな田園地帯を突っ切っていく。



名神高速道を潜ると、東海道新幹線の高架。新幹線も、もはや近代的とは言えなくなったけれど、それでもこの歴史の地を走り抜けていく姿を見ると隔世の感。
手前で右に進み、井上神社に寄り道。前回、世闇の中で見た社を、朝の日差しの下に見ておくためだ。やっぱり、雰囲気が全然違った。



コースに戻って再び北上開始。竹林から抜けて進むと関ヶ原の集落に戻ってきた。
AM10:36、不破関の角。
――東海自然歩道はここでコースが二手に分かれる。左が、大きくぐるりと関ヶ原を一周して関ヶ原駅に至る周遊コース、右がまっすぐ関ヶ原駅へと向かうコース。


駅へ直接向かうショートカット道にしても、そちらでしか見られない史跡もある。なので、どちらが支線ということは無くて、両方本線なのだろうと思う。
前回は駅へ向かった。今回は、満を持して周遊コースへ。途中、左手の不破関跡に立ち寄る……今日二回目だけれど。次いで右手の不破関資料館へ……こちらは工事中。
藤古川を渡って集落に入る。


集落を抜けると再び景色が開けた。といっても関ヶ原盆地の西端で山が近い。前方に見えているのは国道21号・中山道だ。
歩道橋で国道を渡る。下り立った地点には「これより中山道」の道標が立っている。中山道の旧道だ。そちらへ進む。
家々が並んでいる。途中で右折、JRをトンネルで潜る。レンガ造りのトンネル。



林間の道に入って、車道面から消えていた雪が復活する。と、同時に「→大谷吉隆の墓」の道標。
またしても寄り道決行。濃い林の中の地道を小走りで進んでいく。林が深いので地面の雪は斑模様。
やがて、大谷吉隆の墓に到着。木立の中で、予想通り地味なものだった。



コースに戻る。寄り道に要した時間は10分――走らなかったら倍ぐらいかかるだろうか。
北上を再開、何も無い林道を進む。途中、林の切れる箇所があって、そこから小山が見えた。あれが城山だろうか?
再び林間の道となって、左に城山遊歩道の道標が現われた。山頂まで20分・0.6kmとある。今日の選択は、もちろん寄り道。山道に入って城山登山道を登り始める。



急登は無い。それでも、上っていくにつれて雪は深くなっていく。山頂直下では深さ10cmほどになった。もちろん、先行者はいない。
AM11:35、城山山頂に到着。――松尾山と同じように、あずま屋の広場。ただし上空は開けていて、明るい日差しが真っ白な雪に降り注いでいる。そして、この山頂には紋付の旗は立っていない。関ヶ原の合戦はもっと東で行われたのだ。


どちらかというと、ここは伊吹山への展望台。木立が切れているのも北方のみ。ただ、今の時間、伊吹山は再び雲の中に隠れてしまっていた。
昼食を摂るために20分ほど滞留して、下山開始する。サクサクと下って、コースに復帰。林道を再び北へ向かって歩いていく。緩い下り坂。と、前方が開けた。山間の田園地帯だ。


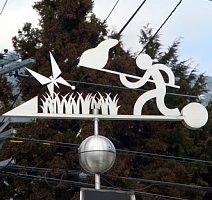


左折して山際を進む。工場の前を過ぎると、エコミュージアム関ヶ原が現われた。自然の展示資料館とのこと。ここにはコース案内図があって、東海自然歩道も緑の線で示されている。
さて、ここから針路は東になる。二車線の県道229号をそのまま歩いていく。暫く歩いて右折、大きく弧を描く関ヶ原バイパスを回り込むようにして東に向かう。


バイパス沿いから離れると、右は関ヶ原ウォーランドの敷地となった。木立で中は覗えない。
――寄り道。次の十字路でウォーランドの入り口まで行ってくる。チラと中を覗く。うーん、色々と素晴らしい……。
コースに戻って小関の集落を抜ける。左折して進路を北に直し、国道365号を歩道橋で越える。






八幡神社の脇から林に入り、木階段を上る。ほどなく、あずま屋のある広場に出た。笹尾山だ。山と言っても小丘。時刻は――PM0:57。

石田三成の紋付き旗が何本も立っている。そう、ここは合戦で石田三成が陣を張った場所だ。関ヶ原の盆地を間近に見下ろすことができるロケーション――その軍勢配置から、西軍の勝利を確信した、かも知れない光景。
今はのどかな田園風景。


お昼時なのに誰もいない。そもそも、わざわざ2月の積雪の日を狙って来るような観光客はいないのかも知れない。
階段を伝って山から下りる。山の麓には何重にも囲われた木柵も再現されていて、東軍の怒涛の攻撃を塞き止めていた様を想像出来るようになっている。
田園地帯を進むと、決戦地。



関ヶ原の戦い最大の激闘地――やっぱり、今の平和な田園風景からそれを想像するのは難しい。なにしろ400年も昔の出来事。それでも、この場所には民家が建たず田園地帯というのも、過去から繋がっている何かがあるからなのかも知れない。
決戦地を後に、そのまま東へ進む。左にローソンをみて関ヶ原バイパスを潜る。少し上がると手前に池が広がった。エコフィールド関ヶ原だ。「熊出没注意」の標示が目立つ。もっとも、この季節は熊は冬眠中の筈。
池の脇の道を進む。途中には野鳥観察の建物などもあって、自然に親しめる趣向になっている。関ヶ原の、血生臭い合戦の史跡群の中にあっては、ほっと息を付ける場所。




八幡池、小栗毛池を巡る。最後の中田池を過ぎると、ベンチのある休憩舎が現われた。公衆トイレもある。
その先、一瞬、山道を辿って丸山。岡山烽火場という、合戦で東軍が開戦の狼煙を上げたという場所だ。陣は黒田長政と竹中重門……なのに、旗は黒田のものばかり。


というわけで、ようやく関ヶ原の合戦史跡の最初のものに辿り着いた。東海自然歩道を東から西へ歩いているのなら、この開戦の狼煙場を最初に目にすることになるので、ここからぐるりと巡って西首塚で終わるという、時間順に合った歩きとなりそう。でも、今日は逆。歴史を過去に遡っている印象が残った。
最後、関ヶ原の地を見晴らす。


丸山から下りる。車道に出るとコースは右……だけれど左折して瑞竜寺へ寄り道。
コースに戻って坂道を下る。T字路があって、「垂井町4.5km」の道標が立っている。東海自然歩道はここを左折して東海、さらに関東を目指している。ただ、ここに東海自然歩道の文字は無い。
今日のところは直進。
先のコースへ進む→ |


南下して国道21号の関ヶ原バイパスに当たる。ここには横断歩道が無くて、代わりに地下道で国道を越える。
相川を橋で渡ると、まっすぐな道。右手には工場の敷地が続いて退屈。
JR東海道線に当たり、潜って越える。右折すると、すぐに関ヶ原駅に到着した。PM1:58。
――これで関ヶ原一周の完成。
JR関ヶ原駅~JR醒ヶ井駅=(JR東海道線)…


ゆっくり歩いても時間が余ってしまった。駅から帰路につくには勿体無い時間だ。まあ、予想もしていたので、ここからさらに歩き繋ぐことも計画していた。
(案1)関ヶ原の中心に点在する残りの史跡を巡る
(案2)中山道を辿る
選択は2。なんとなく歩き足りないので、距離が稼げる方を選んだのだ。というわけで、これから中山道を西へ辿る。
――まずは駅前の道を南に歩いて国道21号・中山道に出る。関ヶ原本陣跡、脇本陣などを見て東進。ただ、国道は車の交通量が多いので途中から左の一本裏手の道に逃げる。と、それが東海自然歩道。朝に歩いた道をまた歩く。不破関跡も、今日3度目の立ち寄り。


国道21号の歩道橋を渡って中山道旧道に入る。右に曲がっていく東海自然歩道を見送って、ようやく初めての道の歩きとなった。すぐに鶯の滝、さらに常盤御前の墓。
民家が消え、登り坂となった。再び東海道線を潜って、小さな峠を越える――ここが今須峠。


下りていく先は今須の集落――岐阜県最後の集落だ。いったん国道21号に合流したけれど、すぐに左手に旧道が逸れていく。そちらへ。
西日の照りつける中、西に向かって歩を進めていく。今須の集落を過ぎると、東海道線を今度は踏み切りで越える。


現われたのが、近江・美濃国境。小さな溝の左右に「岐阜県」「滋賀県」と標示が立っている。「寝物語の里」の史跡もある。
ひょいと越える――もう、ここは関西。さらに傾きを増した西日に向かって、中山道旧道を手繰っていく。
右手には伊吹山が大きく見えてきた。いつしか雲は取れていた。


柏原の集落に入った。こちらも中山道の宿場町で、雰囲気のある家並みが続いている。
途中、JR柏原駅に寄る。ここから列車に乗って帰っても良いのだけど……まだ日没までは時間がある。もう少し歩こう、と決断。
駅前には中部北陸自然歩道の道標が立っていた。いつかこの道も歩く日がやってくるだろうか?


西へ向かってさらに歩く。中部北陸自然歩道は、柏原一里塚の先で北へ向かって折れていった。暫く山際の田園地帯歩き。
国道21号と名神高速道が左から近づいてきて、併走するようになる。右には梓川。暫く粘っていたけれど、山間の狭隘部に入って国道に合流。
左に旧道が逸れる。醒ヶ井だ。


加茂神社に上って、醒ヶ井の集落を見晴らす。日没の時間を迎えて、町は黄昏に沈もうとしていた。日は長くなってきたけれど、寒さは厳しくなる一方。そろそろ今日の歩きもオシマイだ。
再び中部北陸自然歩道の道標が現われた。少し辿ってみたけれど途中で離脱。
JR醒ヶ井駅にはPM5:49に到着。